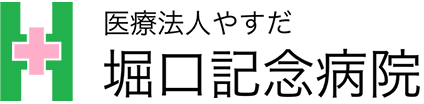もの忘れ外来のご案内
もの忘れとは、
「記憶の一部が保持されなかったり、適切に想起できなかったりする状態」を指します。医学的には「記憶障害(memory impairment)」の一種であり、加齢に伴う生理的な変化として現れることもあれば、認知症や脳の疾患などの初期症状として見られることもあります。
記憶は、
「記銘(覚える)」
「保持(保つ)」
「想起(思い出す)」
という3つの過程から成り立っています。もの忘れはこのいずれかの機能がうまく働かないことによって起こります。
加齢によるもの忘れでは、
「名前がすぐに出てこない」
「予定をうっかり忘れる」
といったエピソード記憶の軽度な障害が中心で、日常生活への影響は少ないことが多いです。一方で、認知症の初期には、何度も同じことを繰り返し尋ねる、経験自体を忘れるといった特徴が見られ、日常生活に支障をきたすことがあります。
もの忘れの背景には、アルツハイマー型認知症、脳血管性認知症、うつ病、薬の副作用、甲状腺機能低下症、ビタミン欠乏症など、様々な要因が関与していることがあります。早期に原因を見極め、適切な対応を行うことで、進行を抑えたり改善が期待できるケースもあります。
受診の目安
- 日常生活で繰り返し同じことを忘れる。
- 何十回行ってきた手順が突然思い出せない。
- 新しいことを覚えるのが難しくなった。
- 記憶が徐々に薄れていくことを感じる。
- 家族の名前が出てこない。
- 会話の中で言葉が出てこないことが増えた。
- 物事に対する関心が低くなり、意欲が減少した。
これらの症状が現れだしたら、もの忘れや認知機能の低下が進行している可能性があります。専門医に早期のご相談ください。
ご家族様へ
患者様ご自身は「もの忘れ」について、まったく気付いていないことがあります。ご家族様が日常生活の中で、次のようなエピソードが見られたり、“あれっ?”と感じた瞬間が受診時期かもしれません。
- 以前は問題なく一人で出来ていたものができなくなってきている。
- 料理をはじめても作り終えることなく途中から別のことをはじめている。
- 何度も同じことを繰り返し尋ねる。
- 直近の出来事は記憶していないが何年も前のことを最近の出来事のように話す。
- ことあるごとに同じことを繰り返し話す。
- 迷子になる。
- 目がうつろだ。一点をボーっと見つめていることがある。
診療の流れ
患者様ご自身は「もの忘れ」について、まったく気付いていないことがあります。ご家族様が日常生活の中で、次のようなエピソードが見られたり、“あれっ?”と感じた瞬間が受診時期かもしれません。
- 問診と症状の確認
患者様の現在の症状や生活背景、病歴などを詳しくお伺いし、もの忘れの原因を特定します。 - 認知機能検査
記憶力や判断力、注意力などを測る検査を行い、認知症の可能性を早期に見つけます。 - 画像検査
必要に応じて、脳のMRIやCTスキャンを実施し、脳の状態を確認します。 - 治療方針の決定
診断に基づき、薬物療法など、個別の治療プランをご提案します。 - 定期フォロー
診断結果に応じた治療を開始し、定期的にフォローアップを行います。
受診にあたってのお願い
患者様ご自身は「もの忘れ」について、まったく気付いていないことがあります。ご家族様が日常生活の中で、次のようなエピソードが見られたり、“あれっ?”と感じた瞬間が受診時期かもしれません。
- ご家族様の方の同伴受診をお願いいたします。
認知機能に関する症状は、ご本人だけではなくご家族様にも影響を及ぼすことがあります。受診時に、ご家族様の方と一緒にお越しいただくと、症状の詳細な把握が行えることで治療方針の決定に役立ちます。 - メモや記録をお持ちください。
日常生活で感じた症状や出来事など、その具体的なエピソードをメモしておき診察時にご持参ください。
※各科の外来診察予定はこちらから